はじめての成人式振袖レンタル!
安心できる基礎知識
振袖の豆知識
着物の合わせ「右前・左前」どっちが正しい?間違えNGな理由と覚え方

目次
成人式や卒業式で振袖を着る際に必ず覚えておきたいのが「着物の合わせ方」。
着物は「右前」と「左前」があり、正しいのはどちらなのかご存じでしょうか?
実はこの合わせ方には大切な意味があり、間違えてしまうと縁起が悪いとされることも。
本記事では、着物の合わせ方「右前・左前」の意味や違い、間違えやすいポイント、正しい覚え方を初心者にもわかりやすく解説します。
成人式の振袖を美しく着こなすために、ぜひ参考にしてください。
着物の「右前・左前」とは?意味と違いを理解しよう

着物を着るうえで、最も基本的で絶対に守らなければならないのが「合わせ方」です。
現代の洋服に慣れた私たちにとっては少し分かりにくいのですが、着物には「右前(みぎまえ)」と「左前(ひだりまえ)」という二種類の着方があります。
そして、生きている人が日常や晴れの日に着る場合は、必ず「右前」が正しい着方とされています。
「右前」が正しい合わせ方
具体的には、まず着物を羽織った際に右側の身頃(体の右半分を覆う布)が体に近い位置に来るようにして着付けを行います。
その上から、左側の身頃を重ねて覆い隠すのです。
つまり外から見たときには「左の衿(えり)が上に重なっている」状態になります。
慣れない方は「右前」という言葉を聞いて「右の布が上に重なるのかな?」と思いがちですが、実際には逆。
右が内側で左が外側というのが正しい「右前」です。

この「右前」というルールは、振袖や訪問着といった女性の着物だけでなく、男性用の紋付袴や普段着の小紋など、和服全般に共通する基本中の基本。
つまり男女問わず、誰がどんなシーンで着物を着る場合にも共通して「右前」である必要があります。
さらに「右前」は実用的な理由からも理にかなっています。
衿を左で上から重ねることで、利き手が多い右手で衿元を押さえたり、懐(ふところ)に手を入れたりしやすくなるのです。
古くから武士や町人が生活の中で着物を着ていた時代、右手で動作を行いやすくするためにも自然と「右前」が定着していきました。
「左前」はなぜNGなのか?
では、なぜ「左前」は間違いとされるのでしょうか。
最大の理由は、左前は死者に着せる衣装の合わせ方だからです。
亡くなった方に納棺の際に着せる死装束は、必ず「左前」で整えられます。
これは仏教の教えや日本の葬送文化に深く関係しており、「生と死を分けるための決まりごと」として古くから続いてきました。
そのため、生きている人が「左前」で着物を着てしまうと、周囲からは「不幸を招く」「縁起が悪い」と受け止められてしまいます。
特に、成人式や結婚式、卒業式といったお祝いの席で「左前」で登場してしまうと、「死装束を連想させる」ために場の雰囲気を損ねかねません。
ご本人が気づかなくても、親族や年配の方から「着方が逆ですよ」と指摘されてしまうこともあります。
また、見た目の印象としても「左前」はどこか不自然に映ります。
衿が逆に重なっているため、正しい着付けを知っている人から見るとすぐに違和感を覚えるのです。
写真に残した際にも衿元が乱れて見えることがあり、一生の記念となる成人式の振袖姿には絶対に避けたい着方と言えるでしょう。
晴れの日にこそ「右前」を意識して

振袖は一生に一度の成人式を飾る特別な衣装です。
華やかな柄や色彩だけでなく、着付けの作法ひとつで印象は大きく変わります。
せっかく選んだお気に入りの振袖も、「左前」で着てしまえば意味を失ってしまうどころか、縁起が悪い着姿になってしまうのです。
だからこそ、着付けをプロに任せる場合であっても、自分自身が「右前が正しい」という知識を持っていることが大切。
事前に基本を知っておくだけで、安心して式典や撮影に臨むことができます。
間違えやすい理由とよくある勘違い
着物を着るときに「右前」と「左前」を混同してしまう人は少なくありません。
普段、和服に馴染みのない生活を送っていると、「どちらが正解なのか」と戸惑ってしまうのも当然のことです。
ここでは、特に初心者が間違えやすい理由や、実際によくある勘違いについて詳しく見ていきましょう。
「右前=右が上」と勘違いしてしまう
最も多い誤解が、「右前」という言葉の受け取り方です。
多くの人は「右前」と聞くと「右側の布を前に出す」「右が上になる」という意味に思えてしまいます。
しかし実際の意味はまったく逆。「右前」とは右の布を先に体に当て、左の布を上から重ねることを指しています。

つまり、見た目には左側の衿が外に出ている状態が正しい「右前」なのです。
洋服の「右打ち」「右折」のように“右を前に出す”という感覚で考えると、間違いやすいのも無理はありません。
言葉の印象に惑わされず、「右は内側」と覚えることが大切です。
鏡の前だと左右が逆に見えて混乱する
着物を着付けるとき、多くの方は鏡を見ながら衿元を整えます。
ところが、鏡に映った自分を見て左右を判断しようとすると、どうしても逆に感じてしまい混乱してしまいます。
特に着付けに慣れていない初心者ほど、「あれ、どっちが上だったかな?」と迷い、結果的に左前にしてしまうケースが多いのです。

また、利き手が左の方も要注意。
普段の動作が右利きの人とは逆になるため、直感的に布を反対側から重ねてしまうことがよくあります。
こうした小さな思い込みが、着付けの大きな間違いにつながるのです。
正しい「右前」の覚え方
着物の正しい着方が「右前」であることは理解できても、実際に自分で着るときには混乱してしまう方も少なくありません。
特に普段から和服に馴染みがない方にとっては、「どちらを上にすればいいのか」が最大の難関となります。
そこで、初心者でも間違えずに覚えられる実践的な方法をいくつかご紹介します。
覚え方①:洋服とは逆と覚える

もっとも分かりやすいのは、「洋服と着物は逆」と意識することです。
洋服の場合、女性用シャツは左手前にボタンが付いているため、「左側の布を手前にして重ねる」仕立てになっています。
一方で着物は、必ず右側の布が内側に隠れ、左側が上に重なるのが正解です。
つまり、「普段の洋服の感覚で合わせると間違える。着物はその逆!」と意識するだけでも、大きな防止策になります。
成人式や卒業式の前に「洋服とは逆!」と声に出して練習すると記憶に残りやすいでしょう。
覚え方②:財布や懐に例える

着物の合わせ方を生活のイメージに置き換えると理解がぐっと簡単になります。
例えば「財布」や「内ポケット」を思い浮かべてみましょう。
懐(ふところ)に大切なものを入れるとき、右手を使って内側に差し込む方が自然です。
そのため、右側の布を体に近づけて内側にしまい込み、左の布でフタをするように重ねると考えると、しっくりくるのではないでしょうか。
江戸時代の町人や武士も同じように右手で懐に小銭や印籠を入れたと言われています。
こうした歴史的な実用性を意識すると、「なるほど、だから右前なんだ」と納得しやすくなります。
覚え方③:漢字の意味から覚える

言葉そのものに注目するのも効果的です。
多くの人が誤解するのは「右前=右が前に出る」というイメージ。
しかし、本来の「前」という字には「先に」「手前に」という意味があり、「右を先に体に当てて、左を重ねる」という解釈が正しいのです。
つまり「右を前に着る→右を先に合わせる→右が内側」と順を追って考えれば、自然と正しいイメージが定着します。
日本語の成り立ちを手がかりにすることで、勘違いが起きにくくなるのです。
覚え方④:写真や実物で確認する

文章だけではどうしても理解が曖昧になりがちです。
そこでおすすめなのが、写真や実物の着姿を繰り返し確認することです。
成人式のカタログや振袖レンタル店のサイトには、必ず正しく着付けされたモデル写真が掲載されています。
「衿の左側が必ず上に重なっている」という状態を目で見て覚え、実際に自分の衿元を鏡で照らし合わせることで、混乱を防げます。
特に振袖を試着する際には、スタッフに「これが右前ですよね?」と確認しながら着ると、体感的に記憶に残りやすいでしょう。
「左前」で着てしまったらどうなる?
着物を正しく着るうえで大切なのは「右前」であること。
しかし、慣れない人が自分で着付けをすると、無意識のうちに「左前」にしてしまうことがあります。
では、もし間違えて「左前」で着てしまった場合、どのような影響があるのでしょうか。
見た目として不自然に映る
まず第一に、「左前」は見た目に違和感を与えます。
衿の重なりが逆になっているため、正しく着られた着物姿に比べると、どこかアンバランスで不格好に見えてしまうのです。
写真に残した際には、この違和感がさらに強調されます。
成人式や卒業式など、一生に一度の晴れの日に残る写真で衿元が逆になってしまうのは、非常にもったいない失敗です。
縁起が悪いとされる
「左前」は亡くなった方に着せる死装束の合わせ方であるため、生きている人が着ると「縁起が悪い」とされています。
特に冠婚葬祭の場においては、周囲の人が敏感に気づくことも多く、「あの子、衿が逆じゃない?」と囁かれてしまうことも。
本人に悪意がなくても、「死装束を連想させる」ことから、ご親族や年配の方々に心配をかけてしまう可能性があります。
華やかでおめでたい振袖姿だからこそ、縁起を担いで正しい着方を心がけたいものです。
恥をかいてしまう可能性がある
成人式や卒業式の会場では、たくさんの人が振袖や袴を着ています。
その中で「左前」のまま参加すると、和装に詳しい方から必ず指摘されるでしょう。
自分では気づかずにいても、周囲から「それ逆だよ」と声をかけられると、恥ずかしい思いをしてしまいます。
特に式典や集合写真の直前に気づかされた場合、慌てて着直す必要があり、時間的にも精神的にも大きな負担になります。
気づいたときの対処法
もし着物を「左前」で着てしまっていることに気づいた場合、どうすればよいのでしょうか。
基本的には、帯を外して最初から着直す必要があります。下に重ねている長襦袢の衿元も「左前」になっていることが多いため、振袖と合わせて必ず直しましょう。
撮影や式典の直前に気づいた場合は、無理に自分だけで直そうとせず、周囲の方や着付けのスタッフに頼るのが安心です。
特に振袖は帯や小物の数が多く複雑なため、自力で整えるのは困難です。
プロの手を借りれば、短時間で美しく、確実に直すことができます。

事前にチェックして防ぐ
こうした失敗を防ぐためには、事前のセルフチェックが欠かせません。
鏡に向かって「左の衿が外側に重なっているか」を確認する習慣をつけましょう。
家族や友人に「これで右前になってる?」と声をかけてもらうのも効果的です。
また、成人式や卒業式の当日は、着付けが済んだら必ずスタッフや写真館の人に「衿合わせが合っているか」確認してもらうと安心です。

成人式の振袖でも「右前」は必須!
成人式は、一生に一度しかない大切な節目の行事です。
華やかな振袖を身にまとい、家族や友人と記念の写真を撮り、これから大人として歩み始める姿を披露する特別な日。
だからこそ、振袖を正しく着ることはとても重要です。
その中でも「右前」で衿を合わせることは、見た目の美しさだけでなく、文化的にも意味のある絶対に外せないポイントです。

晴れの日だからこそ「正しい着方」が大切
振袖は、未婚女性の第一礼装とされる最も格式高い着物です。
成人式という人生の晴れ舞台では、振袖を着ること自体が大きな意味を持っています。
そんな特別な日に「左前」で着てしまうと、縁起が悪いとされるだけでなく、本人が知らないうちに恥をかいてしまう可能性があります。
会場には多くの人が集まり、周囲には和装に詳しい年配の方もいます。
そうした人々の目から見れば、衿合わせが逆になっているのはすぐに分かってしまいます。せっかくの美しい振袖姿も、「あれ、衿が逆だよ」と囁かれてしまっては残念です。
写真に一生残る「振袖姿」
成人式で撮影する写真やアルバムは、一生の記念になります。
振袖姿を見返すたびに「右前」で美しく着られているかどうかは大きな差となって残ります。もし左前のまま写真を残してしまったら、後から気づいたときに後悔することになるかもしれません。
逆に、正しく右前で着られていれば、衿元はきちんと整い、帯や髪飾りとのバランスも美しく仕上がります。
振袖の華やかさを引き立てるのは、見た目の派手さではなく、基本を守ったきちんとした着付けなのです。

プロに任せると安心感
着物の着付けに慣れていないと、「右前と左前を間違えたらどうしよう」と不安になる方も多いでしょう。
しかし、プロの着付け師に任せれば心配はいりません。
着付け師にとって「右前」で整えるのは基本中の基本であり、衿合わせや帯結びも美しく仕上げてくれます。
さらに、振袖特有の重ね衿や帯揚げなどの小物もバランスよく整えてもらえるため、一生に一度の成人式でも安心して任せることができます。
事前練習で不安をなくす
成人式の当日に初めて振袖を着るのではなく、前撮りや試着のタイミングで「右前」の感覚を体に覚えさせておくことも大切です。
実際に袖を通し、鏡で衿の重なりを確認することで、当日慌てる心配がなくなります。
また、家族に「これで右前になってる?」と確認してもらうのも効果的です。
家族写真を撮るときなども、複数の目でチェックすれば安心です。
着物の合わせでよくある質問(FAQ)

着物の「右前・左前」は、和装に慣れていない方にとって分かりにくいポイントです。
特に成人式や卒業式で初めて振袖や袴を着る方からは、毎年同じような疑問が寄せられます。
ここでは、初心者がつまずきやすい質問をまとめ、分かりやすくお答えします。
Q1. 着物の「右前」とは、どちらが上に重なる状態ですか?
A. 左側の衿が外側に重なっている状態が「右前」です。
言葉だけだと混乱しやすいのですが、「右前=右の身頃を先に体に当て、その上に左の身頃を重ねる」ことを意味します。
見た目には「左の衿が上に出ている」状態が正解です。
写真やカタログで振袖姿を見ながら確認すると覚えやすいでしょう。
Q2. 着物を「左前」に着てしまうとどうなりますか?
A. 左前は死装束の着方で、不祝儀を連想させるため縁起が悪いとされています。
見た目もどこか不自然で、和装に詳しい人からはすぐに指摘されてしまいます。
成人式や卒業式のようなお祝いの場では特に避けるべき着方です。
もし気づいたら、帯を解いて最初から着直す必要があります。
Q3. なぜ着物は「右前」と決まっているのですか?
A. 奈良時代の「衣服令」で右前が定められたことに由来します。
719年、元正天皇が出した法律で、男女ともに右前で着るように統一されました。
加えて、右利きの人が懐に手を入れやすい実用的な理由もあります。
文化的・歴史的な背景に根ざしたルールのため、現代でも守られています。
Q4. 男性と女性で右前・左前のルールは違いますか?
A. 男女ともに必ず「右前」が正解です。
洋服では男女でボタンの位置が異なりますが、着物にはその区別はありません。
紋付き袴を着る男性も、振袖を着る女性も、全て右前です。
性別による違いがないため、覚えやすいルールだといえるでしょう。
Q5. 鏡の前だと左右が分からなくなります。どうすればいいですか?
A. 鏡像に惑わされず「左が外に出る」とだけ覚えましょう。
鏡を見ながら着付けをすると左右が逆に見えて混乱しやすいですが、ポイントはシンプルです。
「衿の左側が外に重なる=右前」と覚えておけば、迷わずに合わせられます。
Q6. 長襦袢や浴衣も「右前」ですか?
A. はい。和服は全て「右前」が基本です。
振袖や訪問着などの礼装だけでなく、長襦袢や浴衣のようなカジュアルな和服もすべて右前です。
例外はなく、亡くなった方に着せる場合のみ左前になります。
Q7. 間違えないためのコツはありますか?
A. 「右は内・左は外」とおまじないのように覚えましょう。
実際に着る前に声に出して確認したり、前撮りの試着時にスタッフへ「これで右前ですよね?」と質問する習慣をつけると安心です。
成人式振袖専門店さがの館ならプロの着付けで安心!
着物の合わせ方を理解していても、実際に振袖を美しく着こなすのは簡単なことではありません。
帯結びや衿元、小物のバランスなど、細かな部分で着姿の印象が大きく変わるからです。
そのため、成人式の振袖はプロの着付け師に任せるのが一番安心です。
そして、成人式の振袖レンタル専門店京都さがの館(京都、大阪梅田、茨木、天王寺、神戸三宮、東京池袋、神奈川横浜)なら、着付けから前撮り撮影、当日のヘアセットまでトータルでサポートさせていただくため、初めての方でも不安なく成人式を迎えることができます。

豊富なデザインと安心のレンタル・購入プラン
さがの館では、古典柄から最新トレンドを取り入れたモダンな振袖まで、数百点以上のバリエーションをご用意しています。
レンタルでも購入でも、お客様のご要望に合わせたプランを選べるのが大きな特長です。
さらに、プランには小物のレンタル・着付け・ヘアセット・前撮り撮影などが含まれており、一度のご契約で成人式に必要な準備がすべて整います。

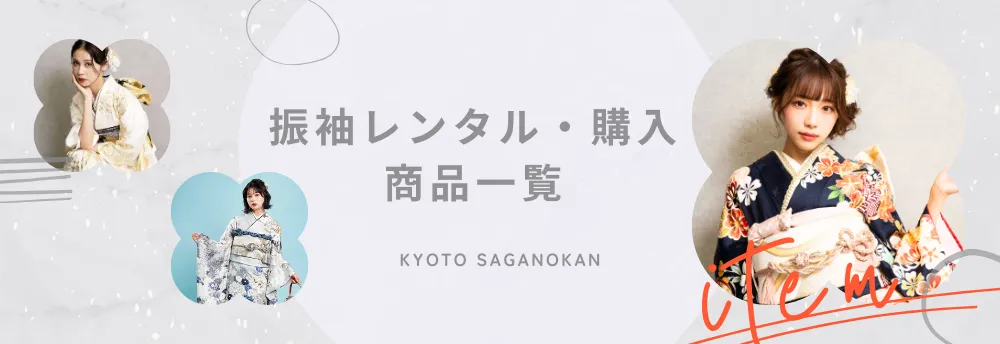
プロの着付け師が丁寧にサポート
振袖の着付けは、帯結び一つでも沢山のバリエーションがあり、専門的な技術が必要です。さがの館では、経験豊富な着付け師が「右前」での衿合わせはもちろん、帯や小物の位置を一人ひとりに合わせて美しく仕上げます。
特に振袖特有の重ね衿や帯揚げ・帯締めのコーディネートは、プロに任せることで華やかさと上品さを兼ね備えた仕上がりになります。

前撮りも当日もトータルサポート
成人式当日だけでなく、前撮り撮影も大切な思い出のひとつ。
さがの館では専用スタジオでプロのカメラマンが撮影を担当し、家族写真やアルバム制作までサポートします。
当日の支度では、朝早くからヘアメイク・着付けまでワンストップで整えてるので、式典会場にも安心して向かえます。

自分に合ったトータルコーディネート
振袖選びでは、着物本体の柄や色だけでなく、帯や小物との組み合わせが印象を大きく左右します。
京都さがの館の各店舗(京都、大阪梅田、茨木、天王寺、神戸三宮、東京池袋、神奈川横浜)のスタッフは、豊富な経験をもとに顔立ちや体型、肌の色に合わせたコーディネートを提案。
プロならではの視点でトータルコーディネートをお手伝いします。

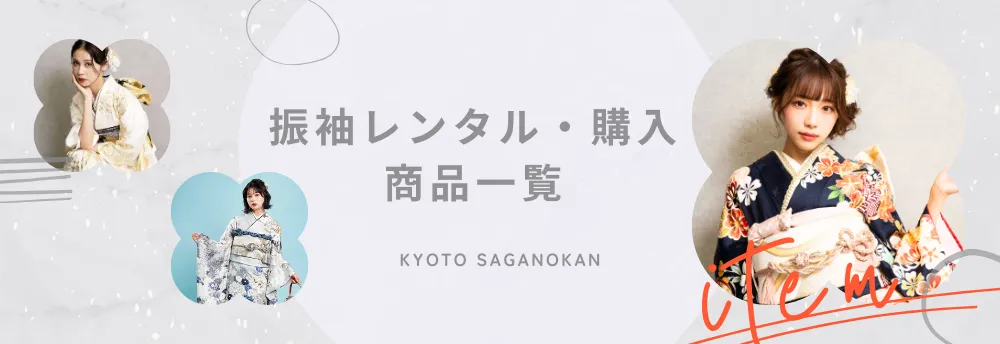
来店予約でさらに安心
振袖の試着や相談は、事前に来店予約をしていただくとスムーズです。
予約すれば待ち時間なくスタッフが対応し、じっくりと振袖選びやコーディネートのご相談が可能です。
また、早期予約特典として「当日支度無料」や「割引特典」がつくこともあります。

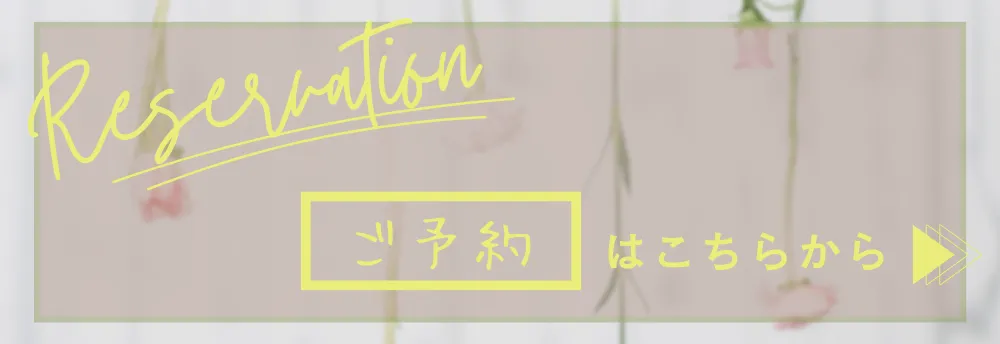
【成人式振袖レンタル・購入の京都さがの館の来店予約はこちら】
まとめ
着物の「右前・左前」は、単なる衿合わせの違いではなく、日本の伝統文化に根ざした大切なルールです。
右前は「生きている人が着る正しい着方」であり、左前は死装束を意味するため絶対に避けるべきもの。
成人式や卒業式など人生の節目には、正しい知識を身につけて美しい振袖姿を残すことが大切です。
プロの着付けと自分自身の理解を両立させ、一生に一度の晴れの日を安心して迎えましょう。
あわせて読みたいコラム一覧
・成人式のお祝い完全ガイド|相場・メッセージ・プレゼントまで徹底解説
・振袖ってクリーニングが必要?着用後に失敗しないお手入れの基本
・成人式で女性も袴を着られる?振袖と袴のメリット・デメリット

